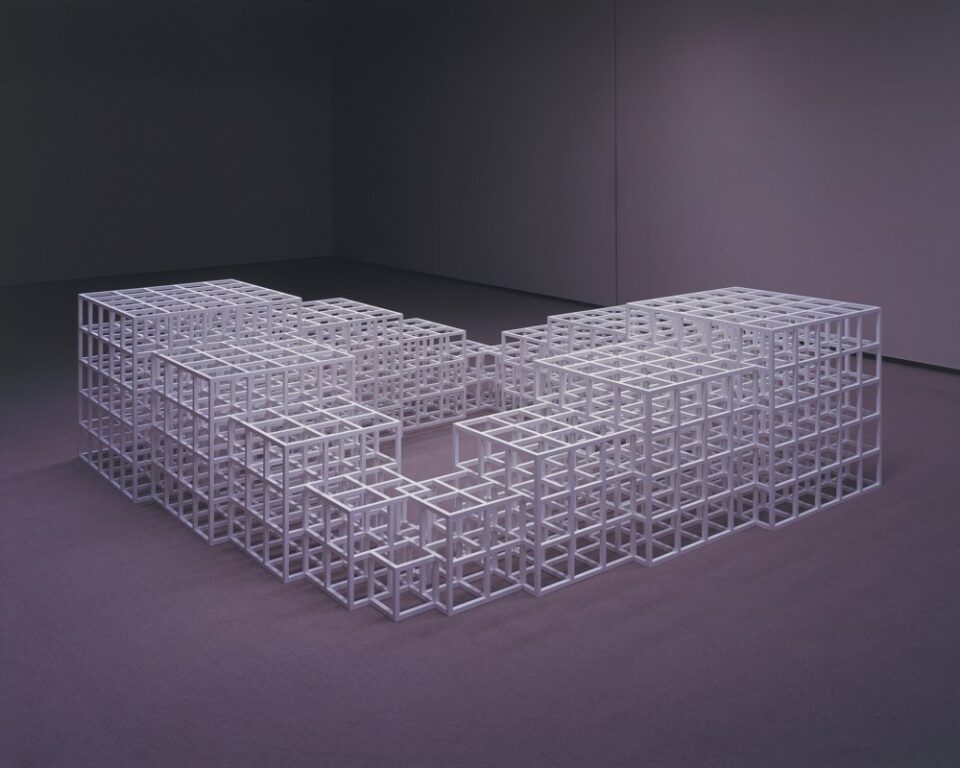現代社会を覆うデジタル技術は、あらゆる事象を0か1かの二進法で切り取っていく。そこには曖昧さの入り込む隙間はなく、極めて明快で効率的だ。しかし、私たちの心身は、その合理的な断層の間に漂う「曖昧な揺らぎ」こそを呼吸し、糧としているのではないだろうか。効率の名の下に削ぎ落とされた「間」や、一見無用に見える不完全なノイズの中にこそ、人間らしさの核心が眠っているように思えてならない。
例えば、思考を文字にする行為を考えてみよう。キーボードを叩き、整然としたフォントを並べる作業は迅速だ。だが、あえて手書きでものを書くとき、私たちはいつもと違う思考の流れを覚える。スイッチを無機質に叩くのではなく、ペン先で文字を「描く」という身体的な行為。それが思惟の微かな輪郭を丁寧になぞり、結果としてタイピングでは到達できない深い思索の入口へと、私たちを誘ってくれるのである。
この「一回性」の重みは、かつての写真文化にも通じている。フィルムの一枚一枚に真剣に向き合った時代、シャッターを切る瞬間には、失敗が許されない独特の緊張感が漂っていた。その「あともどりできない」という感覚こそが、被写体への深い集中力の源となっていたはずだ。指先一つでいくらでも撮り直しができ、即座に消去できるデジタル環境は、果たして表現の質を向上させたのだろうか。便利さと引き換えに、私たちは一瞬に懸ける熱量をどこかに置き忘れてきたのかもしれない。
同様のことは、音楽制作の現場でも言える。テープ録音が主流だった時代、編集技術の限界ゆえに、バンドは「せーの」で一斉に演奏する一発録りを強いられた。不自然な修正を排し、スピード感とライブ感を最優先したその手法は、技術的な完璧さには欠けるかもしれない。しかし、そこには計算では生み出せない熱量と魂が封じ込められていた。現代の完璧なエディットが失ってしまった「生」の迫力が、アナログの不自由さの中には確かに存在していたのである。
アナログからデジタルへの移行は、不要な要素を削ぎ落とす「省略の追求」の歴史でもあった。だが、私たちが効率化のために排除してきた「ノイズ」にこそ、実は物事の本質が潜んでいたのではないだろうか。余計なものを捨て去った結果、私たちは知らぬ間に、人間として最も大切な豊かさを失うという、とんでもない大損をしてしまった可能性がある。
社会の技術は極限へと向かい、AIやデジタルは進化し続ける。しかし、私たちの生身の体は何千年も前からほとんど変わっていない。最新の知性に熱狂しながらも、ふとした瞬間に水の音を聴いて心を鎮めるのが、人間の変わらぬ有りようである。私たちが今、真に進化させるべきは、外部の便利な社会構造ではない。争いを拒絶し、ノイズや揺らぎを慈しむような、自分自身の「内なる精神」の在り方なのではなかろうか。